お守りの起源
遡ること1500年、日本は初めて感染症の大流行に見舞われました。 |
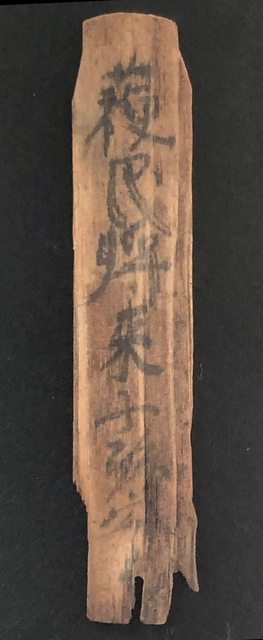 |
お釈迦様の時代にはお寺という概念はなく、一つの場所に定住せずに各地を歩きながら修行をしていました。
しかし、インドでは雨季になると生き物が活動的になり、虫などを踏んで殺してしまうということが起こってしまい、
これが「殺生を行わない」という戒律を犯すことになり問題となりました。そこで雨季の間は無益な殺生を行わないために
外に出歩かないよう、一時的に定住するようになりました。このための住居は各地の支援者から寄進されたものであり、
そこには居住スペースだけでなく、修行の場も造られました。これがお寺の「僧坊」の原型だといわれていて、
時代が進むにつれて一時的な住居から定住の場となり修行者の場へと変化していきました。
遡ること1500年、日本は初めて感染症の大流行に見舞われました。 |
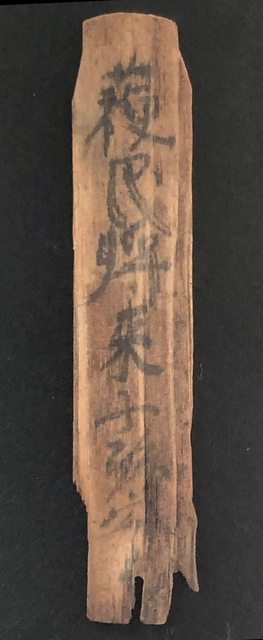 |
そもそも御朱印とは、「書き写したお経を奉納した証」として授与されるものでした。
四国などで御朱印を納経印(のうきょういん)、御朱印帳を納経帳(のうきょうちょう)と呼ぶのはそのためです。
庶民も旅が許された江戸時代、参拝が旅の目的となったことで、寺の周辺は観光地として多くの人が訪れるようになりました。
その後次第に写経の証としての御朱印本来の意味は薄れ、参拝するだけでもいただけるようになります。